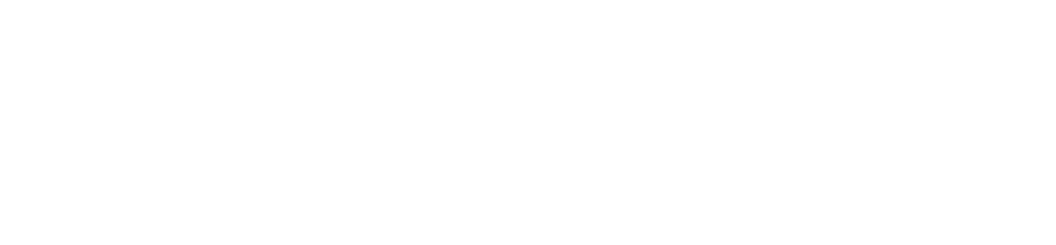Blog
NHKの朝ドラ『あんぱん』のロケ地でも話題の高知県から、全国の自治体で初となるニュースが発表されました。

高知県は、職員の時間外労働(残業)の割増賃金率を2026年度の1年間、実験的に25%から50%に引き上げる条例案を県議会に提出すると発表しました。
全国紙やテレビでも取り上げられたこの動きは、長時間労働からの脱却に向けた大きな一歩として注目を集めています。
今回の取り組みは、働き方改革の分野で第一人者である株式会社ワークライフバランスさんの協力によって実現したとのこと。会見した浜田省司知事は「男性中心の働き方では続かない。人口減少先行県の高知県だからこそ、最先端の働き方改革に取り組み全国をリードしたい」と話されました。
Career Bloomも、女性推進やサステナブルな働き方を支援する立場として、この動きにはとても大きな意味があると感じています。
なぜ「1.5倍」が注目されているのか?
現在の日本の時間外割増率は1.25倍と、先進国の中では比較的低い水準にあります。
一方、海外では1.5倍以上を標準とする国も多く、休日労働はさらに高い割増率が設定されている例もあります。
また、厚生労働省の試算によると、1.44倍を超える水準なら企業は「残業を頼むより新しい人を雇う」という発想に切り替わりやすいといわれています。
もちろんこれは一つの考え方にすぎませんが、今回の高知県の決断は、その境目をどう働き方に反映させるかを探る取り組みとしての意味味合いを持つのかもしれません。
制度だけでなく「文化」も問われる
”制度を変えれば現場の行動も変わる!”…ならば良いのですが、なかなか一筋縄ではいかないのが現状です。
「残業を減らすこと」が心理的なプレッシャーになり、かえって働きにくさにつながるケースもあると耳にしたりもします。
だからこそ、制度と並行して
- ・業務の見える化や分担の仕組みづくり
- ・短時間で成果を出すマネジメントスタイルの模索
- ・多様な人材が安心して力を発揮できる文化づくり
といった側面も大切ではないかと私たちは考えています。
自分たちの組織に置き換えてみる
もし自社で時間外割増率が1.5倍になったら?
例えば「残業を減らして短時間正社員を採用する」などのシナリオを試算すると、コストや成果の面でも新しい可能性が見えるかもしれません。
もちろん、業種や規模によって最適解は異なると思いますが、「残業に依存しない働き方」を一度シミュレーションしてみること自体が有益なことかもしれない、と今回の発表を見て考えさせられました。
私たちが感じたこと
今回の高知県の発表を受けて、「制度」と「文化」を両輪で動かすことの重要性を改めて感じました。
女性推進やサステナブルな働き方の実現を目指す私たちとしては、課題意識そのものがこのニュースをきっかけに広がっていったら良いなという想いを持ちつつ、企業ごとの状況に合った変化の方法を一緒に考えていきたいと思っています。
まとめ
高知県の挑戦は、日本の働き方に関する議論を大きく前進させる出来事でした。
皆さんの組織では、この動きをどのように受け止めますか?
ぜひ「自分たちにとってのサステナブルな働き方」について、社内で話し合うきっかけにしていただければと思います。
▽関連リンク
この記事を書いた人:阪口裕子( 研修イベント企画・ライフキャリアコーチ)
大阪で子育てをしながら、フルリモート勤務中。元営業現場の最前線&高校の先生という経験を活かし、キャリアと子育てのリアルに向き合いながら、「すべての人が自分らしく働ける社会」を目指して日々試行錯誤しています。「家族と週末どこで楽しく過ごそう?」を考えるのがささやかな楽しみ。おいしいお酒も好きです🥂