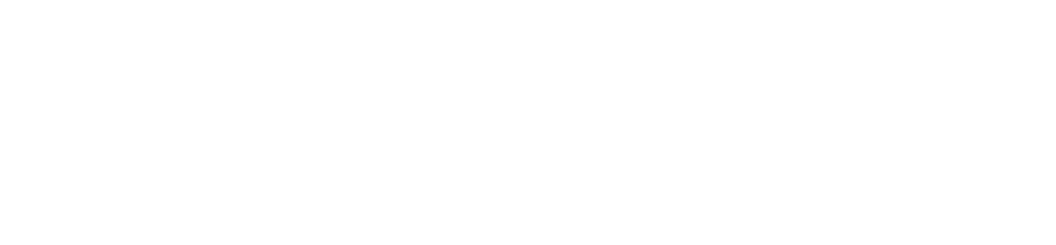Blog
近年、教育現場でも「DEI&B(多様性・公平性・包摂性・帰属感)」という考え方を取り入れる動きが広がってきています。
学生や教職員の多様化が進むなか、「誰もが安心して学び・働ける環境を整える」ことは、教育機関にとって一層重要な課題となりつつあるのではないでしょうか。
また、このテーマは企業における人材マネジメントや職場づくりとも重なる部分が多いように思います。
本日は、上智大学が発行している“DEI&Bハンドブック”を拝見して感じたことを共有したいと思います。
DEIからDEI&Bへ
- Diversity(多様性):国籍・性別・年齢・宗教・障害の有無などを尊重すること
- Equity(公平性):状況に応じて適切な支援を行うこと
- Inclusion(包摂性):誰もが安心して声を上げられる環境を整えること
- Belonging(帰属感):組織の中で「自分の居場所がある」と感じられる状態
「DEI」という言葉が日本で話題になり始めてから、すでに10年以上が経過したでしょうか。
近年ではそこに「Belonging(帰属感)」が加わり、制度整備に加えて“心理的なつながり”をどう生み出していくかが注目されるようになっています。
大学の取り組み事例
先日、上智大学のDEI&Bハンドブックを拝見する機会がありました。
上智大学ではこのようなハンドブックを公開し、ジェンダー、LGBTQ+、障害、育児・介護といった幅広いテーマを整理し、学生・教職員にわかりやすく提示しています。
詳細はこちら:https://www.sophia.ac.jp/assets/uploads/2025/09/771cced488902997e6880cafa78ea9cd.pdf
とても示唆に富む内容で、他大学の取り組みについても関心が高まりました。調べてみると、東京都立大学では「多様な性に関するハンドブック」を発行していたり、東京大学では「インクルージョンの指針(Index for Inclusion)」を翻訳・活用し、教育現場での実践を推進しています。教育機関の意識も少しずつ変化してきている印象を受けます。
宣言や方針を掲げる大学は増えてきましたが、「現場での具体的な行動につながるツール」としてハンドブックを整備している例は、まだ多くはないようです。
企業にとってのヒント
こうした大学の取り組みからは、企業にとっても学べる点が多いと感じます。
ハンドブックを整備することによって、
- 理念を具体化できる:抽象的な「多様性推進」を、現場で実行可能な指針に落とし込める
- 共通理解を促すことができる:全員が同じ情報にアクセスでき、価値観の共有が進む
- 文化づくりにつながる:制度だけでなく、日常の意識や行動を変えるきっかけになり得る
といった効果が期待されます。
まとめ
上智大学が発行したDEI&Bハンドブックは、「誰もが居場所を感じられる環境」を形にするための具体的なツールとして参考になる事例だと思います。
特に、学生や教職員が「どこに相談すればいいのか」「どんな制度があるのか」を事前に知ることが出来るのは、大きな安心感につながりますよね。
わからない時に正しくアクセスできる情報が整理されていることが、組織への“信頼感”を育むと感じます。これは企業や行政にも共通するテーマではないでしょうか。
制度や数値の整備だけでなく、従業員一人ひとりのBelongingをどう支え、安心して働ける環境をつくっていくかが問われているように思います。
あなたの職場では、「困ったときに安心して頼れる情報」や「自分の居場所があると感じられる仕組み」は整っているでしょうか。
Career Bloomでは、インナーブランディングとアウターブランディングのそれぞれを連動させることで、より企業の魅力が高まるお手伝いをしています。
是非、考えるきっかけにしていただけたら嬉しいです。
▽関連リンク
この記事を書いた人:阪口裕子( 研修イベント企画・ライフキャリアコーチ)
大阪で子育てをしながら、フルリモート勤務中。元営業現場の最前線&高校の先生という経験を活かし、キャリアと子育てのリアルに向き合いながら、「すべての人が自分らしく働ける社会」を目指して日々試行錯誤しています。「家族と週末どこで楽しく過ごそう?」を考えるのがささやかな楽しみ。おいしいお酒も好きです🥂