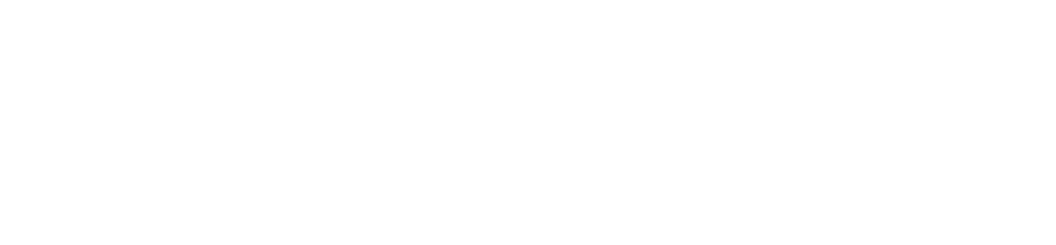Bloom talk



保育サービス「ステラ」やコンシェルジェサービス・家事代行サービスを展開し、「生活総合支援サービス」の発展に尽力してきた植田貴世子さん。革新的なサービスを次々と生み出した秘訣と、現代社会で生きる女性たちに伝えたいメッセージとは?
「企業が歩み寄るべき」いち早くテレワークを導入

−株式会社クラッシーが社内で働く女性たちに対して取り組んできたことはありますか?
植田:家庭という場で営まれている暮らしが整っていてこそ、いい仕事ができるものですし、人は「企業のためではなく幸せになるために生きている」と思っているので、そこで生まれる仕事上の制約は企業が歩み寄るべきだと思っています。ましてや子どもは国の未来であり、社会全体で守るべき存在です。親に限らず、大人の究極の存在意義は子どもを守ることだと考えています。ですから、「子どもが熱を出して迎えに行かなければいけない」と相談されれば、「子どもが熱を出したのだから当たり前でしょう。どうぞ行っていらっしゃい」と言って送り出しました。最初は社員も目を丸くしていましたが、今では子育てをしながら長年働き続けてくれる社員が多いです。
篠崎:そういう会社なら働き続けたいと誰もが思うはずです。
植田:子どもがいるために出張できない社員も多かったので、かなり早期、2008年頃だったでしょうか、テレビ会議システムを導入しました。そういった環境整備は企業がやるべきだと思います。子どもが熱を出しているのに仕事を取れなんて、あり得ないことだと思います。
子どもの将来を見据えた「本気保育」

−ステラは英語だけでなく、食育や音育、体育など独自の保育プログラムを展開しています。これらのプログラムはどう開発されたのでしょうか。
植田:我々はいわゆる保育園ではありません。「時代が求める新たな子育て支援機関」として、保護者様と同じ目線で同じ景色を見るという考え方を持っています。仕事と家事、育児を両立されているパパ・ママのご不安は、私自身も同じように経験してきました。ですから、その不安を解消したり、子どもにこういう時間を持って欲しいという願いを叶えられるような環境作りに努めています。
ステラの保育は、子どもの10年、20年先の将来を考えた時に必要とされる資質で、しかも特に乳幼児期に身につけるべきものをプログラムに反映しています。創業当初は「Global」がKeywordとなり、英語と保育の一体化した保育プログラムを開発しました。我々の英語教育は、子どもの言語機能の発達段階にそって実施しますので、子どもには全く無理なく吸収されます。
昨今では働きながら子育てをするご家庭が増え、子どもが保育施設で過ごす時間が増えています。今までは親の背中を見て、ご飯の作り方や掃除の仕方、郵便の出し方など暮らしの術を身につけてきましたが、今の子どもたちは家でそれらを見て学ぶ時間が減っています。そこで、2010年、私たちは暮らしの術を子ども達が学習できるようお洗濯やお掃除、お料理等を取り入れた暮らしと保育がの一体化した保育プログラムを開発しました。
篠崎:保育とそういう風に向き合っていらっしゃるんですね。本気保育(英語・体育・音育・食育)のプログラムはどのようにして生まれましたか?

植田:2018年から取り組んでいるプラグラムです。今の子どもたちが大人になる頃は、間違いなくICT社会になっています。人間の仕事がICT・IoT・AIに代替されることも増える中で、人間が持つ唯一の力となるであろう「心力」を鍛えなければなりません。「心力」を鍛えるためには、情操教育で心をたくさん動かすことが必要だと考えました。感動したり、驚いたり、感激したり。心を動かすには「本物」に触れることが大切です。そこで陸上競技の日本代表育成コーチの監修による「本気体育」、世界で活躍するオーケストラ指揮者の監修による「本気音育」などの開発に至りました。
篠崎:まさに各界のプロが保育に携わっているわけですね。

植田:通常、保育現場はジェネラリストである保育士が携わりますが、私たちの保育空間では外大、音大、体育大卒者が保育士資格をとり、それぞれの専門性を活かしつつ保育にあたっています。時代の進化に伴い、新たなプログラムを今後も開発していくと思います。
篠崎:親と「同じ目線で同じ景色を見る」という視点が体現されていると思いますし、それが、ステラが熱狂的に支持される理由なのだと思います。今日取材にお伺いしたステラプリスクール南青山では、アフリカの教育・雇用の創出を目的とするNPO法人CLOUDYとコラボレーションし、ガーナで活躍するCLOUDYのデザイナーが描いたオリジナルテキスタイルが描かれています。

植田:子ども達にエシカルやSDGsに関心も寄せて欲しいし、何よりも幸せの形は様々あるという事を体得してもらうための取り組みの1つです。他にもお手洗いに徳島の藍を利用した陶器を取り入れたり、殺菌効果が高く、うがい手洗いなどにも使える高機能電解イオンミスト「STELLA×IELU」を導入したりと子どもを取り巻く環境にステラのこだわりが詰まっています。

家庭の日常生活習慣を乱さない家事代行サービス
−家事代行サービスにおいても、前編でお話しされた高品質なサービスを提供するための管理が徹底されています。また決められたプランではなく、まずコンシェルジェが要望や家事の手順を確認し、フルカスタマイズでサービスを提供するのが特徴的ですよね。
植田:誰しも日常生活習慣というのがあると思うのですが、それはその人の不安や恐れ、備え、願望が反映されて習慣になっているものだということが我々独自の日記調査を通じて分かりました。ですから、我々がご家庭に入らせていただいて、その日常生活習慣を乱すことは絶対にあってはなりませんし、お客様の居心地の悪さに繋がると考えています。私たちのやり方を押し付けるのではなく、お客様流をいち早く見つけ、お客様流に暮らしを整えて帰ってくる。もちろん「こうすると良いかもしれません」というご提案はしますが、勝手にお客様の習慣を乱すことはしないんです。
篠崎:ある意味、他社のサービスとは真逆にも思えるやり方ですが、確かに家庭には自分なりの法則みたいなものがあるものですよね。そういったサービスはどのような考え方から生まれたのでしょうか。
植田:家庭は「家族の幸せの製造工場」であり、「家族の心の写真」だと思います。人の幸せの根源にある暮らしを整える場に入らせていただくのですから、そこでその家庭のやり方を尊重するのは当然であり、最も重要なことだと思っています。
篠崎:そういったお考えは、お母様の影響が大きいのでしょうか。
植田:そうですね。母は日本の家庭料理研究の第一人者、土井勝さんから直接お料理の手ほどきを受けたと聞いていますが、お料理はもちろん、歳時記の知識を身につけ、設いに心を砕き、食卓には路端で摘んだ花を飾っていました。この暮らしの風景を私は「豊かなる日常」と名付けています。そんな母の手伝いを日々する中で、暮らしを大切にする姿勢を学んだように思います。また私自身が母となってから改めて、子どもが未来に身につけておくべきことは何かを考え、今を大切に過ごさなければならないのだと感じるようになりました。この視点がステラのプログラムにも反映されています。
女性が「賢明な声」を挙げて欲しい

篠崎:ご著書『暮らし上手は幸せ上手』の中で、コンシェルジェの面接に来た主婦の方々が「家事しかできない」「子育て経験しかない」と言っていて、そのスキル・経験がいかに活きるかを植田さんが熱弁されたというエピソードが印象的でした。
植田:オフィスで働いているか、家庭で働いているかの違いがあるだけであって、家事や育児もいわゆる仕事と同様・同等の能力が求められます。家事というのは家を政ること、Home Managementですから仕事にこそ価値があって、暮らしには価値がないという高度経済成長期の価値観に惑わされずにいて欲しいという思いが強くありました。「家族の幸せの製造工場」で、幸せを作っていた女性が、いかに能力が高く素晴らしいか。
よく「子育ての負担軽減」「子育てをはじめると生産性が下がる」などと言われますが、子育ては「負担」ではない、「喜び」です。日本の未来を作っているんですよ。こんな凄い仕事はありません。日本の未来を作っているのに、「生産性が低い」のでしょうか、子育てこそ最も生産性の高い仕事であり、これこそ男性社会の好きな「常識」とやらですし、女性自身にも改めてそう認識をいただきたいと思っています。
篠崎:本当にそうですね。女性も家事育児を過小評価せず、自信を持って良いと思います。女性の意識変革も必要ですね。
植田:男性ももちろん意識を変えていただきたいのですが、女性自身にも家事や育児の価値に気づいて欲しいですし、社会に出て「賢明な声」を挙げてほしいとずっと思っていました。あえて言わせていただくなら、今女性が少し浮かれてしまっていないかという心配があります。かつて男性がそうしたように、暮らしを軽んじてしまっているのではないかと。
これは手作りの料理じゃなければいけないとか、家事育児にもっと時間をかけてとか、そういうことではないんです。ただ「家庭が家族の幸せの製造工場」だという意識を忘れないで、家庭と向き合っていただきたい。そうでなければ、子どもたちの居場所がなくなってしまいます。「暮らし上手は幸せ上手」、人が幸せに暮らすために、暮らしをもう一度大切に考えてみて欲しいです。
篠崎:暮らしを大切にできているかと問われると、私自身も反省が多くあります。女性に対しても厳しく愛のあるメッセージをしてくださる植田さんは改めて素敵だなと感じました。
植田:女性たちがご自身の人生を生きていらっしゃる様子を見るのが私にとってはこの上ない喜びなんです。ステラにきてくださるお母様方も、悩みながらも輝いていらっしゃいます。年に何度か「おしゃべりテーブル」という子育てのご相談もお受けする機会があるのですが、少しでも子育てを楽しんでいただきたいという思いがあります。家事代行サービスも、永遠に続く家事を少しでも支援させていただきたいという思いから始まりました。
自分の人生をどう生きたいか?人生設計を定めて

篠崎:私の世代は周囲の友人も含め、仕事と家庭との両立に悩んでいる世代だと思います。親は専業主婦が当たり前だった時代でもあり、ロールモデルがいないという苦しさもあります。そういった女性に言葉をかけるとしたらどんな言葉になりますか。
植田:私は男性であれ女性であれ、多様な選択肢が等しくあるべきだと思います。そういった点では女性が選択をできない社会というのは変わるべきだと思っていたけれども、主体的にそれを選択し、決断したのであればそこに正直に努力をする必要があるとも思います。女性であることに甘えてはいけないです。
まずは自分の人生をどう生きたいか、人生設計をしっかりとするべきではないでしょうか。自分がどう生きたいかが定まれば、「こう生きたいからここで挫けちゃだめだな」とか「こう生きたいから今日は帰ります」とか判断し、毅然と物言えるじゃないですか。そういう人たちが束になれば、パワーになり、世の中を変えていく力になると思います。
篠崎:確かに自分の中で定まっていないからこそ、「周囲にはこう言われる」「会社ではこういうことを求められる」と迷いが生まれるのかもしれないですね。
私も女性の活躍推進に携わらせていただく中で、1人では無理だなと思うことが本当に多いですし、一緒に「束」になって変えていきたいと強く思います。植田さんはまさに変革の先頭ですね。
植田:次にバトンを渡すために自分たちの世代ができることは何かを考え、私の世代の役割を果たすべく闘ってきただけで、肩にすごい力が入っていたわけではないんです。全然足りていないですけれど、主張すべきことは主張してきたし、やるべきことはやってきたかなと。次の時代にやわらかな社会を繋ぎたい、という思いで走り続けてきました。
篠崎:繋いできてくださったバトンをしっかりと受け取り、私も頑張っていきたいと思います。「暮らしが人生の真ん中にある」そして「人は幸せになるために生きている」この普遍的なことを大切にして私も働いていきたいです。私も決意を新たにする時間となりました。本日はありがとうございました。
おすすめ記事はこちら

【イベントレポート】大塚ちづるが語る「My Value〜セルフジャッジの罠〜」

【植田貴世子×篠崎侑美】「人は幸せになるために生きている」女性起業家のパイオニアが立ち向かった逆風【前編】