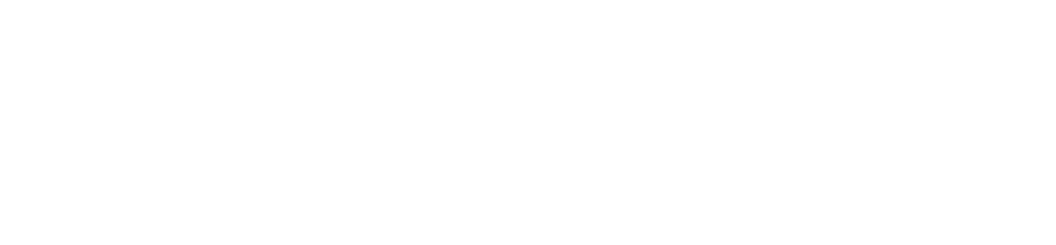Bloom talk



保育サービス「ステラ」やコンシェルジェサービス・家事代行サービスを展開し、「生活総合支援サービス」の発展に尽力してきた植田貴世子さんは、女性起業家のパイオニアでもある。社会の逆風にどう立ち向かってきたのだろうか。篠崎侑美(Career Bloom株式会社/代表取締役社長)との対談を前編・後編でお届けする。
「指輪や車は自分で買いたい!」自己実現の意識から就職

−植田さんは1986年、男女雇用機会均等法が制定された翌年に保育サービス「ステラ」を創業されました。創業前も通訳・翻訳の仕事をされ、「働く女性」の最前線にいらっしゃったと思います。当時は四大卒の女性が会社勤めをすることは稀で、会社に勤めても結婚をしたら家庭に入るのが当たり前とされていた時代に、植田さんはなぜ働くことを選んだのでしょうか。
植田:私は1955年に生まれ、まさに高度経済成長期に価値観形成をしてきた世代です。戦後の効率的な経済復興のために、男性は仕事、女性は家事と役割分担がされていて、女性は結婚して家庭に入るのが当たり前という時代でした。でも私は「指輪や車は夫に買ってもらうのではなくて、自分の力で買いたい」と単純にそう思ったんです。自分の力で働いて得たお金で、自分の好きなものを買いたいという人として素直な気持ちであり、つまりは自己実現をしたかったのだと思います。けれど、当時の女性には専門職以外はコピー取りやお茶汲みのような仕事しかありません。そういう仕事では指輪や車を買えるようなお給料は頂けないので、大学を卒業後に英語専門学校に入り直して、通訳・翻訳の専門職に就くことにしました。
篠崎:その後、アメリカで事業をされていたと伺いましたが、通訳・翻訳のお仕事でしょうか。
植田:通訳・翻訳の仕事でも海外出張はありましたが、アメリカに行ったのは結婚して、夫とハワイでフードビジネスの事業に携わることになったからです。当時、アメリカが国策として力を入れていたファストフードのフランチャイズビジネスに挑戦しました。
篠崎:いきなり海外でのビジネスの挑戦、その行動力に驚きます。
植田:一言で言えば、“苦しかった”ですね。そもそも経済の勉強もしたことはないので、ビジネスについての知識は全くありませんでしたし、日本とは生活文化もビジネス社会の仕組みも違います。いくら英語が喋れても、すぐに社会に溶け込めるわけではないのだと実感しました。厳しい環境でビジネスのノウハウを叩き込まれたので、今の自分の糧になってはいるのですが、当時はとてもしんどかったです。
篠崎:しかもご子息が生まれて、まさに仕事と育児の両立に悩まれたと思います。当時、アメリカの女性たちはどのように働いていましたか。
植田:アメリカではレーガン政権時に大規模な規制改革がなされ、経済構造や産業構造がガラリと変わる時期でした。段々と、ピンヒールを履いた女性がホテルのロビーでノートパソコンを持って仕事をする姿を見るようになって、女性もこうやって働く時代が来るのだなと実感したのを覚えています。
父から学んだ、失敗を恐れない前進力
−アメリカに5年間滞在され、帰国後は起業の道を選ばれました。鉄工所から独立し、起業したお父様の影響もあったのでしょうか。
植田:そうですね。父は30歳の時に起業しました。父の背中を見ながら育って感じたのは、壁にぶち当たったり失敗したりしても、あきらめずに前を見据えてもがき続ければ、必ず“解”は見出せるということです。だから失敗することへの恐怖心はなく、とにかくやろうと思うことがあるならやってみようという前進力を、父の生き様から学びました。
また、日本に戻ってきてからは、シングルマザーとして働きながら当時2歳の息子を育てなければいけないという現実もありました。当時日本に唯一あったアメリカ資本の派遣会社に登録すると様々な仕事をご紹介いただけたのですが、子育てをするに十分な収入を得られる仕事は夜遅くまで働く必要がありました。保育園は17時に終わってしまうので、息子を預ける場所がありません。どう考えても会社勤めと子育ての両立は難しく、起業しか選択肢はないと思いました。
篠崎:延長保育という概念もなく、子育てをしながら働く女性にとって本当に厳しい環境だったと思います。起業も大変だったのではないでしょうか。
植田:40年ほど前の話ではあるのですが女性は当時、マンションの賃貸ですら保証人がいないと契約できない時代でした。当然、起業のための融資なんて話も聞いてもらえませんでしたね。またステラの構想はあったものの、知名度や実績のない保育園に子どもの命を預けるはずがありません。そこで、まず自宅で出来る英語教室の講師を始め、一定の収益を得ながら地域の皆さんからの認知度向上・信頼構築に繋げることにしました。1年間の準備期間を経て起業しましたが、その後もしばらく講師を続けていました。
篠崎:英語を取り入れた保育サービス「ステラ」の構想はどのように生まれましたか。

植田:アメリカで事業をやっていたとは言え、ビジネス経験が多いわけではなかったので、起業しようと思いたったところですぐに起業のシーズを思いつけたわけではありません。ただ考えても考えても自分の中にある素材というのは、母性と、女性性と、英語しかなく…。これを知恵と工夫で編み上げることで、ステラが生まれました。子ども達が生きるであろう20年先を見据え“国際化”に着目し、英語と保育が一体化した保育プログラムを考案。さらに朝8時から夜8時まで年中無休という具合に保育に自由度を加え認可保育園との差別化を図りました。育児ノイローゼなどの言葉が出現し、子育て中の孤立や不安に関心が集まり出していた当時、お子様をお預かりし、お母様たちがお食事やファッションショーなど、自分時間を楽しめるイベントも企画していきました。
篠崎:女性の社会進出に伴って、子育てに寄り添うサービスの出現はまさに救世主ですね。
社会の逆風を受けても「心しなやかに」
−事業は順調に拡大したのでしょうか。
植田:地域のご利用者は相当なスピードで増えていきましたが、まず事業化を図るにはやはり売り上げの安定のための法人利用や前向きな投資のための金融機関からの融資が必要になります。当然、経済社会との繋がりも作っていかなければいけないわけですが、「子育て支援にお金を投じる価値があるのか」となかなか事業を理解して頂けず、社会の逆風を感じました。企業内託児の営業に行くと、「会社に来て子育ての話をするとは何事だ」と名刺を投げ返されることもありました。
でもこういった社会の逆風が私の中では健全な闘志に変わっていきました。ここで私が諦めたら、世の女性が浮かばれない。そう思って、どんな対応をされても、とにかく営業活動だけは続けようと決意しました。大企業の社長に直談判したり、理解しやすいようなデータやエビデンス重視の資料を作成してプレゼンしたり。その結果、製薬会社さんや、看護師不足が深刻化していた医師会が法人契約をしてくださり、事業の弾みとなりました。

篠崎:今では考えられないような言動を目の当たりにされたと思います。その闘いがいかに困難だったか想像に難くないですが、どのように立ち向かって行かれたのでしょうか。
植田:逆風に立ち向かうためには、闘い方を考えますよね。そうすると段々と社会の仕組み−つまり重厚長大型の経済至上主義、利益至上主義に基づいた価値観が見えてくるようになりました。いわゆる「24時間働けますか」という言葉がテレビで当たり前のように宣伝される時代です。
でも私は、こう考えたんです。「人は幸せになるために生きているのであって、会社のために生きているわけではない」。仕事も、経済・政治・教育・法律も、人が幸せになるために生まれたもの。それなのにいつの間にか手段がひとり歩きし、人の幸せという目的に逆行するような社会構造になってしまっている。この現状を、私たちの次世代にそのまま手渡すわけにはいかないという一使命感にも似た強い決意が芽生えました。株式会社クラッシーの「心やわらかに 仕事しなやかに」というモットーはここから生まれました。
篠崎:人は幸せになるために生きている。当たり前のようで、ハッとさせられる言葉です。
植田:「心やわらかに」というのはある意味、自分を守るための言葉でもあったと思います。女性らしさは失わずに、ビジネスで自己実現したかったのです。男性社会の中では、私の考え方や行動が「一般的な価値観とは異なる、非常識だ」と非難されても、いつかその非常識が常識に変わる時代が来ると信じていましたし、その頃の社会的しがらみのない私たち女性が世界を変えていくしかないとすら思っていました。
一方で、信頼して頂くには実績の裏付けがいるというのも真実です。社会からも、ご利用者からも信頼される企業になるためには、やはり実績は必要です。事業の正当性を訴え続けるだけでなく、たとえばISO認証(※)を取得し、サービス価値を可視化できるよう努めました。
※ ISO認証制度とは、認証(審査登録)機関であるJQAが、組織の構築したマネジメントシステムが規格の要求事項に適合しているか審査し、適合していればその組織を登録する制度。品質の高い製品・サービスを提供できる能力があることを証明することができる。
篠崎:男性中心の経済社会であることを実感するタイミングが多くあったと思いますが、そこに順応しようとせず、女性らしくビジネスに向き合われたことが今のクラッシーに繋がっているのだと感じます。
植田:例えば企業に訪問すると女性用のトイレが離れた場所にしかなかったり、スカートでは座りにくいソファ席が基本だったりと、男性型社会を実感するタイミングは多かったです。でも私は男性ではなく女性で、考え方も違えば、ビジネスでのアプローチも違います。女性ならではの働き方や考え方もあっていいはず。違いがあって当然だという考え方で事業と向き合ってきましたし、社会に「協調」や「適応」はしても自らを失くしてまで「同調」や「順応」はしないという心意気を大切にしてきました。
−事業としての信頼を「仕事しなやかに」積み重ねてこられたのですね。最終的に、金融機関からの融資があったのはいつ頃でしょうか。
植田:銀行に融資を頂けたのは、創業してから15年の月日が経った2001年頃です。シリコンバレーが脚光を浴びて、世界中に起業ブームが起こったころ女性の起業家も少しずつ注目を集め始めた時期でした。何年も何度も金融機関に通い続け、ようやくお借りした資金で関西進出を図りました。
篠崎:2001年ってつい最近ですよね。15年もの間、実績を積み重ねてこられたにも拘らず、融資に至らなかったというのはもどかしかったと思います。諦めそうになる瞬間はなかったのですか?
植田:私は何かを決断したら、それをどう具現化するかを考え、策を講じて実行するという生き方なので、打たれてもたたかれても実現できる方法を考え、それを実行するということを、ただただ愚直に続けてきました。起業を決めるまでには様々なことを考えましたが、「やろうと決めたからには継続する」というのが自分の根底にありました。
篠崎:お父様から受け継がれた、失敗を恐れずに前進し続ける姿勢ですね。
家庭は「家族の幸せの製造工場」
−植田さんご自身は、仕事と家庭のバランスをどのように取ってこられましたか。
植田:仕事と家庭の両立に関しても、「人は幸せになるために生きている」という考え方がベースになっていたと思います。「仕事に行くか、家族を取るか」など大事な選択を迫られるタイミングは幾度となくありましたが、その都度、どうすることが一番自分にとって心地よく、嘘なく自己実現できるかという、明確な基準を持って判断するようにしていました。自分の中で基準があれば、「この日は絶対に授業参観に行く」「今日はどうしても外せない仕事があるから仕事を優先する」と迷いなく判断することができます。
篠崎:どちらかを取るのではなく、そのタイミングごとに自らが幸せになるために必要なことを選択していくのですね。
植田:どちらか一方を選択しなければいけないというのは、これまでの男性型常識だと思います。当たり前に、どちらも大事です。子どもが熱を出していれば、そばに居てやるのは当たり前ですし、だからと言って仕事を軽んじているわけではもちろんありません。
篠崎:本当にそうですよね。ちなみに、植田さんにとって、プライベートな幸せはどのような瞬間ですか?
植田:スポーツ観戦も大好きですし、観劇も楽しみます。でも1人でお料理したり部屋の片付けや模様替えをしたり、家事に熱中している時間が至福ですね。家庭は「家族の幸せの製造工場」であり、「家族の心の写真」です。自分の錨を下ろす住まい、暮らしが整ってこそ、いい仕事・いい子育て、ひいてはいい人生が紡げるんだと思います。ですから私も家族と過ごす時間やプライベートの時間は大切にしていますし、そういう暮らしを整えるためにも、むろん自身の知恵と工夫、賢明な努力は不可欠ですが、企業ももっと「人」に歩み寄るべきだと思います。
苦境だからこそ生まれた盤石なサービス品質

−植田さんがこれまで一番の苦境だと感じたのはいつですか?
植田:2008年のリーマンショックには大きな影響を受けました。ちょうど関西・関東・名古屋と三大都市圏に進出し、投資を回収しようという時期に売上が低迷し、会社として非常に厳しい状況に陥りました。「息をするのもしんどい」時期でした。それでも、今できることは何かを懸命に考え、サービスやノウハウの徹底的な言語化・マニュアル化を行いました。まずは足元の仕組みを見直し、整えることこそ、その時に私たちができる最善の選択だと強く感じたからです。これが「品質のクラッシー」と呼ばれる今に繋がったと思います。
篠崎:どのようにマニュアル化を進められたのでしょうか。
植田:社員が共通言語で語れるよう、用語の定義や職務の定義を明確にし、定期的に組織で意識共有ができる仕組みを整えました。また、誰もが高品質なサービスを継続的に提供できるよう全てのサービス工程・行為を細分化しました。たとえば家事代行サービスにおける「洗濯」であれば、洋服を仕分けし、洗濯機にかけ、干して、取り込んで、たたんで、アイロンをかけ、収納する…と7つの工程に分けられます。さらに1つ1つの工程であるべき行為を定義しました。ものづくりのプロセスになぞらえて、サービスデザインを施し、一つ一つ仕組み化していきました。
篠崎:もの凄い量ですね。目に見えないとされるサービス業を徹底的に細分化して形に落とし込んでいかれたのですね。
植田:家事代行サービスにおいては時代における暮らしの変遷を把握するため、定期的に日記調査を行うようにしています。どんなライフステージ、ライフスタイルの暮らしびとがリビングでどのくらいの時間をどのように過ごすのか、何を工夫し、どういう食生活をしているのか等、生活習慣を見聞き知ることでよりお客様の暮らしに寄り添ったサービスをご提供できるようになったと思います。
篠崎:徹底的なマーケティング調査まで!だからこそ時代のニーズを掴むサービスを生み出し続けられているのですね。多くの方に支持されるサービスの秘訣についてはこの後、改めてお伺いできればと思います。
後編に続く
おすすめ記事はこちら

【イベントレポート】大塚ちづるが語る「My Value〜セルフジャッジの罠〜」

【植田貴世子×篠崎侑美】「子育ては未来をつくる仕事」女性の経験に価値を見出す保育と家事支援【後編】